チョイス跳び箱1
公開日: 2025年6月23日月曜日
こんにちは。本校2年目の山本です。
今年は、昨年度担任していた学年を持ち上がり、3年1組の担任をしています。
今年度、個別最適な学びと協働的な学びについて授業実践を通して研究を深めていきたいと思っております。
今回は、3年生の跳び箱運動の学習「チョイス跳び箱」という単元で、子どもたちと集団跳び箱に挑戦してみようとおもっています。この学習では、子どもたちが集団跳び箱のなかで技や難易度を「選択」し、技の出来栄えを高めるために練習の場を「選択」することで子どもたちが自分の課題に合わせて活動を選び、調整していく姿を目指しています。また、子どもたちが選択したそれぞれの場で、教師が効果的に関わっていくための手立てや見取りの方法について追求していきたいと思っています。
早速、第1時の授業を行ったので、その様子をお伝えしたいと思います。
この学年の子どもたちは2年生のことの跳び箱を使った運動遊びの学習で、自分たちで跳び箱を使ったコースをつくりかえながら跳んだり、乗ったり、降りたりする運動を楽しんできました。まずは、そんな子どもたちに「自由に跳び箱を使った運動を行っていいよ」と指示をだしました。子どもたちは、跳び乗ったり、跳び降りたり、開脚跳びをしたり、低い台の上ででんぐり返しをしたりしていました。その後、どんな技があったのか共有する時間を取りました。そこで技を系統ごとに分けていくことで子どもたちには、3年生では遊びではなく技に挑戦していこうと投げかけました。(前単元のマット運動でも技を系統ごとに分けて紹介したので、自然に理解することができていました。)
この後に見つけた技にチャレンジする時間を取る中で、どんどん連続で技に挑戦しているグループがあったので、「せっかくなら一緒に跳んでみたら?」と声をかけることで、友達と「合わせて」跳び箱の技を行うことに着目させました。その姿を全体に紹介することで、本単元の活動である集団跳び箱に出合わせました。その際、その姿を動画に撮り、学習支援アプリで共有し、それぞれで見る時間をとりました。以下その時の子どもたちの様子です。
T 「動画は友達と一緒に見ていいですよ」
CC「面白そう!」「難しそうじゃない?」
C「せーのって言った方がいいんじゃない?」
T「なんでせーのっていうの?」
C「合わせるためです」
T「合わせるって何を?」
CC「走り始めとか」「跳ぶ瞬間とか」「タイミング」
ここまでで、動き始めや跳び終わりなどの「タイミング」を合わせることに価値を感じている子どもたちでした。そんな子どもたちに跳び方や技の出来栄えにも着目して欲しく他に工夫できるところがないかを尋ねました。
T「そんなところを合わせると動画がかっこよくなりそうだね。他にかっこよくするために工夫できそうなことはある?」
C 「走り方とか」
T「たしかに。でも跳んでる最中とかはどう?」
C「足の高さとかがズレてる。なつみさんは足が腰くらいまで上がってるけど、さなとくんは跳び箱の2段目くらい」
T「これも合わせられるとかっこよくなりそう?」
CC「なりそう!」「けどむずかしそう」
T「みんなはどっちにあわせたい?簡単な方?難しい方?」
CC「難しい方」
T「じゃあ、これから出来るわざのレベルアップもしていけるといいね」
こんなやりとりから、とんでいる最中の動きにも目を向けていくことができました。また、本時中の運動の中から、跳び箱は横より縦の方が難しいことや段数が上がったり、跳び箱が長くなると難しくなることにも気づいていたため、全体で共有しました。
次の時間では、最初の動画撮影です。子どもたちは6人1組になり、自分の力に合わせて技を選択しながら始めの姿を記録します。単元終末には、ここで撮影した動画からどれだけレベルアップできたか振り返られるようにしたいと思います。
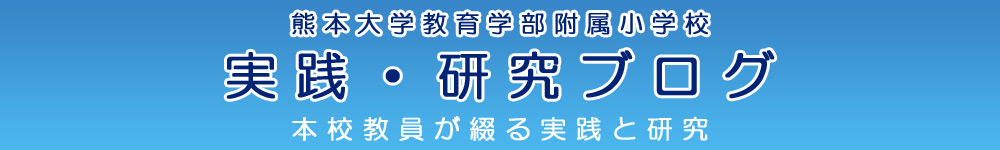
0 件のコメント :
コメントを投稿