チョイス跳び箱3
公開日: 2025年6月25日水曜日
こんにちは。本日、チョイス跳び箱の第3時を行いました。
前時までに、チームで動画を撮り、見返すことで自分の挑戦する技をんだ子どもたちでした。本時では、そんな子どもたちがそれぞれの場に分かれ、技の練習に取り組んでいきました。
授業冒頭、前時までの活動を振り返り、本時の活動場所を挙手で意思表示しました。開脚跳びに22人、台上前転に8人、抱え込み跳びに6人でした。前時の振り返りをもとに予想していた結果より開脚跳びの人数が多くなっていました。(自由に活動の場を選べるので、仲の良い友達と一緒にしたいという人もいたのかもしれません。)その後、それぞれの場所に移り、練習を始めました。
始めの5分間は、各場所を回りながら子どもたちの活動の様子や技の習得状況を見てまわりました。開脚跳びでは、馬乗りまではできるが跳びこすことが難しい子や着手の位置が手前すぎて跳びきれない子が多かったです。また、台上前転では、跳び箱の上で回転することはできるが、上手く着地ができない子や踏切の際に片足ずつ足が上がってしまう子がいました。抱え込み跳びでは、踏切位置が近すぎたため、跳びにくいことに気付き、跳び箱と踏切板を離して練習に取り組んでいたため、踏切調整板を渡しました。
各場を見回った後、台上前転の場、開脚跳びの場、抱え込み跳びの場の順でコツや運動の感覚を共有していきました。以下、子どもたちのやりとりになります。
<台上前転の場>
C1「勢いをつけすぎないほうがいい」
C2「跳び箱の前で一回ジャンプをした方がいい」
T「ジャンプをするってどういうこと?」「こうやってってこと?」(片足踏切をやりながら)
C3「ちょっとやってみていいですか?」→両足踏切でやってみる
CC「ああー」「うまっ」
T「どんなジャンプしてたの?」
CC「両足!」
このようにやり取りをしながら、壁面掲示の連続図に見つけたコツを記入していきました。
こちらが実際の掲示物になります。青で運動のコツを記入し、緑で運動の感覚を記入しています。
その後は見つけたコツを生かしながら練習に取り組み、両足踏切をする姿や回転の際、頭のてっぺんをつけていた子どもが後頭部をつけてスムーズに回るようになったりしていました。
<開脚跳びの場>
C4「踏切は強くジャンプした方がいい」
C5「ターンって感じ」「それだったら結構行けそうな感じ」
C4「トランポリンみたいに」
〜少し空いて〜
C6「踏切につながるんだけど、最初に2・3歩跳んだ方がいい」
T「2・3歩ってどういうこと?」
C6「トン・トン・トーンって」
CC「ああー」
このようにやり取りをしながら、台上前転の場と同様に掲示物にコツや運動の感覚を記入していきました。
その後、開脚跳びの場を見ていると踏切や着手は良くなったものの、なかなか肩を前に出すことができず跳びきれない子どもが4人ほどいました。そこで、跳び箱の両横に低い段数の跳び箱を設置し、そこに乗り、跨った状態から跳び箱に手をつけて跳ぶ練習ができる場を用意しました。なかなか、跳びきれない子どもたちにこの場での練習を促し、何度か挑戦している姿を見て、私は抱え込み跳びの場へと移りました。
抱え込み跳びの場での子どもたちとのやり取りを終えた後、先ほどまで跳べなかった子どもが3人跳べるようになっていました。その中の1人のことなぜ跳べるようになったのかをやり取りすると、「肩を前に出すことがわかった」と言っていました。その時は、このやりとりで終わっていたのですが、給食を食べ終わった後に、教室に掲示している連続図を私が眺めているとその子が話しかけてきたのでその時のやり取りを記します。
C7「先生、私跳び箱のたてで跳ぶことができたから横もやってみたらできました」
T「え!すごいじゃん!なんでできるようになったの?」
C7「肩を前に出すとできるようになりました」
T「なんで肩を前に出せるようになったの?」
C7「私、幼稚園生のときにカエルジャンプで競争したことがあって、その時の感じに似てたから思い出してやってみたらできました」
この子は、跳び箱の動きのコツを過去の運動経験の感覚と結びつけることで、肩を前に出す動きを身につけることができていました。私は、その場で掲示に緑でカエルジャンプのことを書き足しました。このような、学び方を他の子どもたちにも広げることで動きを身につけることができるだろうと感じられる場面でした。
<抱え込み跳びの場>
抱え込み跳びの場では、なかなか足を抜くことができず困っている様子が見られました。技のコツを尋ねると、事前にお手本動画で学習していたことから、膝を胸につけることや手を広くつくなどのコツが見つかりました。けれど、コツはわかっているがなかなかできない様子を見ていたので、困っていることがないかを尋ね、以下のようなやり取りが生まれました。
T「なんか困ってることはないかな?」
C8「斜めになっちゃう」
T「体が?」
C9「手はまっすぐつけるんだけど、(足が横に開いて)手がこうなっちゃう(跳び箱からはなれる)」
T「じゃあ、足が斜めになってしまうことが困りごとだから、どうやったら解決できるかみんなでかんがえてみたら?」
このようなやり取りの後、子どもたちはお手本動画内の練習方法を見たり、友達と話し合いながら解決しようとしていました。しかし、なかなかどうすればいいのか困っていたため、跳び箱の上に抱え込みとびの要領で両足で跳び乗る練習などを提案しました。しかし、今日は授業時間が来たため、ここで活動は終了してしまいました。
これまで「開脚跳びがしたい」や「台上前転を頑張る」などの技そのものを課題としている子どもが多かったのですが、本時の振り返りでは、「開脚跳びの着地のバランスが取れていないから着地をかんぺきにしたい」や「手を遠くにつけると前転するスペースがなくなる」などの技の中のポイントについてやコツについての記述が増えていました。そこで、次時ではさらに課題を焦点化していき、個人で練習したいポイントごとに練習できる場を用意しようと思います。「この技のこの部分ができない」という課題を解決していく授業にしたいと思います。
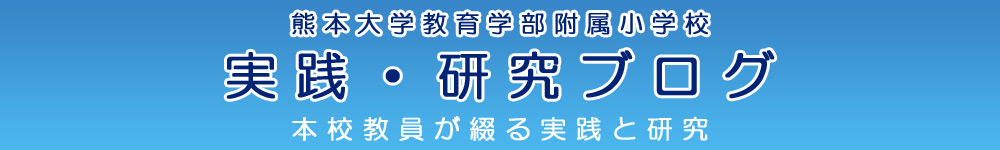






0 件のコメント :
コメントを投稿