第4学年 ゲーム(ゴール型:サッカー)~スフェリカルシュートゲーム~
公開日: 2025年7月8日火曜日
こんにちは。体育科の冨永悠真です。本校1年目になります。
今日は本年度の夏の体育授業研究会で行う『ひらいて、つないで、協力して!~スフェリカルシュートゲーム~』について、簡単に紹介させていただきます。
低学年のボールゲームでは、得点につながる動きを個人で行うことが多いです。一方、高学年のゴール型ゲームでは得点につながる動きを仲間と連携して行うことが多くなります。そこで、中学年のボールゲームでは、集団対集団の攻防をしながら、友達と力を合わせて得点を競い合うゲームを通して、仲間と協力して得点をしたり防いだりするゲームのたのしさに親しんでほしいという願いからスタートしました。また、様々な先生方とお話しする中で、足でのボール操作によるゴール型ゲームを実践する難しさをよく耳にします。(なぜ難しさを感じているのかについては以下で述べたいと思います。)今回は、そのような先生方への思いにこたえて本教材を提案します。
中学年の実態として、自分が得点することのみに執着してしまい、友達の動きやチームの仲間と協力することに目が向いていない子どもが多い現状があると思います。そのような子どもたちが、得点するためにはボールを持たない時の動きが重要であるということに気付き、その動きを友達と共に試行錯誤していってほしいと思っています。また、その中で、仲間と協力してパスをつないで攻撃をしたり、守ったりすることのよさを感じながら、仲間と共に運動をすることのたのしさを味わってほしいと思います。
・味方や空いているスペースにボールをパスしたり、ねらったゴールにシュートをしたりするボール操作。
・シュートしやすい場所に移動したり、ゴールに体を向けたりするボールを持たないときの動き。
よって、先述したような課題から、本実践では、「スフェリカルシュートゲーム」に取り組みます。このゲームの特徴は大きく3つあります。1つ目は、コートです。ゾーンによって攻撃側と守備側を分けているため、ボール保持者へのプレッシャーがなくノーマークで状況判断が可能となります。そのため、意図的なプレーを行いやすくなります。2つ目は、教具です。パックを使用することで、素材がやわらかく、ボールが2次元の動きとなります。そのため、ボール操作が容易となります。また、恐怖心を軽減できより意欲的に取り組むことが可能となります。3つ目は、ゴールです。360度どこからでもシュート可能なゴールにすることで、技能の差関係なく誰でもシュート可能となり、全員参加を保障します。これらの工夫により協力するたのしさを見いだし、今後のゴール型の学習にもつながっていくと考えます。
(図1)
今回はゲームについてお話しました。
体育授業研究会は只今申し込み受付中です。↓
https://sites.google.com/view/taiikujugyokenkyukai/%E3%83%9B%E3%83%BC%E3%83%A0
興味のある方は、ぜひご参加ください!
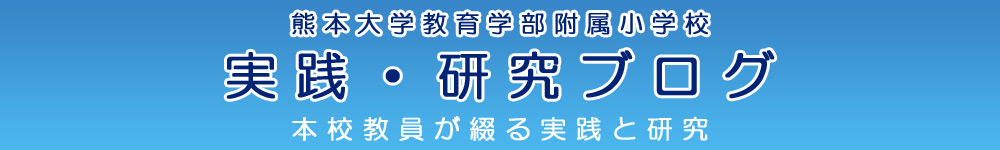

0 件のコメント :
コメントを投稿