【1年:鬼遊び】0_ゲームについて、教師の願い
公開日: 2025年11月21日金曜日
こんにちは、本校6年目、体育科の西です。
本年度は1年生を担任しております。
昨年度までは高学年を担当することが多かったので、ギャップに驚くことも多くありました。動きもその一つで、上靴を立ったまま履くことが難しかったり、階段を降りるときは手すりにつかまらないといけなかったりと、ぎこちなさを感じる場面が多く見られました。
子どもたちと過ごして半年が過ぎ、体育の時間では、体の部位に着目したり「こうしたんだよ」とモデリングしながら友達に伝えたりしながら、学習を進めてきました。また、体育だけでなく、友達や上級生とかかわる中で、様々な動きを獲得し、滑らかに動くことができるようになってきたと感じています。
そんな子どもたちが入学当初からよく遊んでいるのが「鬼ごっこ」です。
体育では「鬼遊び」としてゲーム領域に位置付けられており、中学年以降、主に「ゴール型」の学習に繋がっていきます。
体育では「鬼遊び」としてゲーム領域に位置付けられており、中学年以降、主に「ゴール型」の学習に繋がっていきます。
ゴール型の課題として「何をしたらいいかわからず、動くことができない」ことが挙げられます。これはゲームの判断要素の「空いている空間」や「相手の位置」「ゴール」が見えないこと、自分の役割が明確ではないことが原因と考えています。
低学年の鬼遊びの実践では
○「ゴール」より「目の前にいる相手」の意識が強く、動きの連続性が生まれにくいこと
○「逃げる・追う」のみの関係になっていること
が、ゴール型への接続として難しさを生んでいるのでは、と考えました。
また、目の前の子どもたちに目を向けると
○鬼ごっこで鬼と逃げが入り乱れながら遊びを楽しんでいる
○遊びを楽しむ中で、自然と「空間に走り込む動き」や「相手を突破する動き」が表出している
姿が見られます。
こんな子どもたちに、チームとして運動に取り組む初めての単元で、個人としての動きの質を高めるとともに、「仲間」の存在に気づき、連携して動くたのしさを味わってほしいと願いをもちました。
そこで、ケイドロを基にした運動遊び「まんまるケイドロ」に取り組むことにしました。
コート、ルールは以下の通りです。
そこで、ケイドロを基にした運動遊び「まんまるケイドロ」に取り組むことにしました。
コート、ルールは以下の通りです。

正方形のコートに、ろうやを「まんまる」かつ「まんなか」に設置することで、
○同じ状況が生まれる(4等分)
○鬼も逃げも、常にろうやを意識でき、何を見るかがシンプルかつ明確
○道(空いているスペース)を見つけやすい
→鬼とろうや、鬼とライン、鬼と鬼
また、ケイドロという特性上、子どもの役割が以下のように明確になると考えます。
○逃げの動き:鬼から逃げること、おたすけ(ろうやにいる人を助けにいく)
○ろうやの中:タッチされやすい位置に移動すること
○鬼の動き:逃げを捕まえること、ろうやを守ること
この単元を通して子どもたちに
・空いている場所を見つけて、早く走ったり急に曲がったり、身をかわしたりする動き
・チームで連携して鬼をかわしたり走り抜けたりする動き
を身に付けることをねらいます。
さらに、このような動きを身に付けていく過程で、なぜその動きをしたのか、なぜその動きがよいと感じたかを語らせることで、何を見て自分の動きを判断すればいいかを自覚し、意図的に動こうとする子どもの姿を目指しています。
次回、波乱の単元びらきについてお話します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
体育科 西 沙織
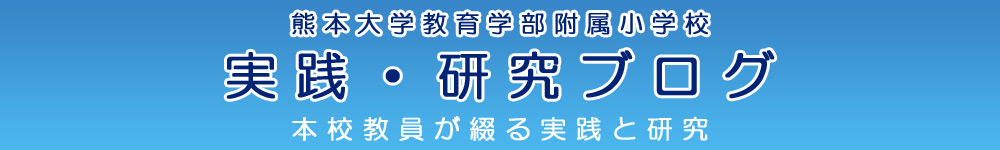
0 件のコメント :
コメントを投稿